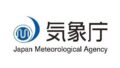「避難場所」と「避難所」は聞いたことがある人も多いかも知れません。
この2つの言葉にはたいへん大きな違いがあります。
「避難場所」と「避難所」
定義による違い
「避難場所」とは、「災害による危険が切迫した状況において、生命の安全を確保することを目的とした緊急に避難する際の避難先です。」、「指定緊急避難場所は、地震、高潮、津波、洪水、土砂災害などの種類ごとに指定されています。」と説明されています。(出典:香川県HP)
「避難所」とは、災害の危険性がなくなった後に、ご自宅が被災された方々や、災害により帰宅が困難となった方々が一時的に滞在することを目的とした施設」のことです。(出典:香川県HP)
つまり、
「避難場所」は災害の危険が迫っているさ中での避難先であることがわかります。
「避難所」は災害発生後の滞在場所のことです。
こういった違いがあります。
したがって、目的が違いますから、当然場所も違ってくることがあるのです。
(同じ場所である場合もありますので念のため。)
図記号による違い
避難場所等の図記号(ロゴ、マーク)は、2016年(平成28)年3月22日に標準化されました。
下図↓は避難場所のロゴになります。(出所:平成28年度版「防災白書」)

「避難場所」(←身の安全が最優先の安全な場所)は一番左のロゴです。
「避難所」(←災害発生後に身を置く場所)は一番右のロゴです。
実際の使われ方
ちなみに、災害種別記号もこの時に制定・改正されました。
下図↓は、避難場所の表示例になります。(出所:平成28年度「防災白書」)

左図は、産業会館という施設が、避難場所として使われるだけでなく、避難所としても使われること、さらには、津波避難ビルとしても使われるということを表示しています。なお、洪水/内水氾濫、津波/高潮、土石流、崖崩れ・地すべりといった災害種別を対象としていることがわかります。一方で、大規模な火事の際には対象としていないことも意味しています。
こういった標示が街中にあると思いますので、ぜひ気に留めて確認してみるのがオススメです!
「避難場所」「避難所」はどこにある?
それでは、「避難場所」や「避難所」の情報は、どこから情報を入手すれば良いでしょうか?
◆入手①:【第5回】でもとり上げた「避難情報」(国土交通省)から確認することもできます。
避難情報が発令された地域における対象エリア内の「開設中の避難場所」が確認できます。
◆入手②:「防災情報 全国避難所ガイド」アプリ
ファーストメディア株式会社が提供する避難所アプリです。
現在地周辺の避難場所等の自動検索や、ハザードマップの表示のほか、防災情報の通知や、
ルート案内で避難支援をしてくれたり、避難所混雑状況なども確認できます。
全国の自治体が定める「避難場所」や「避難所」を15万件以上収録しているようです。
とても使いやすく、日頃の備えとしてはたいへん有用でしょう。
◆入手③:「災救マップ」(Web上)
未来共生災害救援マップ(略称:災救マップ)と言います。
全国の避難所と宗教施設をあわせた約30万件のデータがあるようです。
神社仏閣など宗教施設を重視したリストアップがなされています。
大阪大学大学院と一般社団法人地域情報共創センターにより共同で運営されています。
リンクは貼っていませんが、検索🔍で確認してみてください。
おわりに・・・
「避難場所」は「身の安全を確保」する上でとても大切な情報と言えるでしょう。
とは言え、最も重要なことは身の安全ですから、避難場所への道中の安全配慮も重要です。
災害がまさに迫っている状況でしたら、そのさ中の移動は危険をはらんでいることも
十分に認識した中で行動していただければと思います。
被害の回避行動を早めに行うことができればもちろんよいのでしょう。
ですが、なかなか描いたような理想的な避難行動になるとは限りません。
災害発生の状況の進み方が急激な場合も、やはり、起こり得る話しでもあります。
もし、「浸水が始まっていて夜間のため足元がなかなか確認しづらい」
そういったときは、「その時に最も安全を確実に確保できる避難行動」をして欲しいです。
例えば、自宅にとどまり高いところで過ごす。(垂直避難)
例えば、近くにあるビルの2階、3階を使わせてもらう。(水平避難)
もちろん、土地所有者や住民の感情もあるかも知れませんが、
いわゆる「緊急避難的行動」として、
ぜひとも、「結果無事」「事なきを得た」となるような判断をお願いしたいと思います!
もしも迷ったときは
「大丈夫かな?」とか「たぶん大丈夫だろう」側の選択肢ではなく、
「これはかなり大丈夫だと思う」側の選択肢をとれるようお願いします。
「災害リスクから距離をとる」
=「災害が発生しても影響を受けないところに移動する」
ことが大切です!
知った「今がスタートライン!」